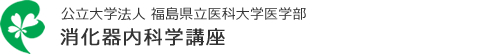国際学会報告
第65回米国肝臓学会 AASLD The Liver Meeting 2014に参加して
阿部 和道
はじめに

学会会場のHynes Convention Center2014年11月7日から11日まで,アメリカで最も伝統的な街の一つであるマサチューセッツ州のボストンで行われた第65回米国肝臓学会(American Association for The Study of Liver Diseases:AASLD)The Liver Meeting 2014へ参加の機会を頂きました。
この時期のニューイングランド地方の紅葉は素晴らしく,5日間いずれも晴天で,すがすがしい雰囲気の中で行われました。
AASLD

会場内AASLDは,肝臓分野で権威のある学会の1つで,毎年ボストンかサンフランシスコ,ワシントンDCで開催されています。世界中から9,500人を超える肝臓病の基礎・臨床に携わる研究者,病理医そしてコメディカルなどが集まり,演題の採択率は50%程度と言われています。
2014年は2,065題が採用されていて,日本の施設からの演題数は200題以上,そのうち20題近くがTop 10%であるPresidential Poster of Distinctionの評価を受けていました。また全採択演題のうち口演発表は240題で,日本人の口演発表は8題のみでした。
当教室からは,高橋先生の「Fast corticosteroid tapering and early fibrosis stages:important risk factors for type 1 autoimmune hepatitis」と私の「Near-infrared spectroscopy for the early detection of prodromal phase of depression during interferon-based therapy for patients with chronic hepatitis C」の2題が採択されました。いずれもポスタープレゼンテーションでの発表でした。
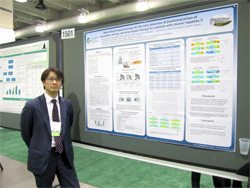 |
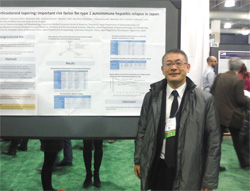 |
| 私のポスター発表 | 高橋先生のポスター発表 |
AASLDのプログラムは非常にタフで、朝6時45分のEarly Morning Workshopから始まり,午前中は主にプレナリー・セッションやレクチャーが行われ,昼にはポスター・セッションやランチョン,そして午後は主にパラレル・セッションが午後6時過ぎまで各会場で続き,さらにその後のサテライト・シンポジウムやSpecial Interest Group Programが終了するのは夜の8時といった具合でした。
ウイルス肝炎分野の占める割合が多く,特に,日本でも治療の進歩が著しいC型肝炎の最新の知見が多数発表されていました。Child B,Cの非代償性肝硬変を伴うC型肝炎患者において,ソホスブビルとレディパスビルの12週にわたる併用療法はSVR率が87%であり,MELDやAlbが改善することが報告されていました。また,アメリカ人研究者に話しかけられ,日本のC型肝炎治療の現状について討論しました。アメリカでも治療が混迷している状況を垣間みました。名刺も交換し,帰国後も連絡をとることとしました。
自己免疫性肝疾患や免疫に関わる演題は95題程度でした。PBCに対するファルネソイドX受容体の刺激薬であるオベチコール酸の有効性についての演題が多数みられました。UDCA抵抗性のPBCに期待されます。またAIHモデルに対してリツキシマブを用いたB細胞の枯渇が有効であるとの口演発表が注目されていました。
Early Morning Workshopsである「Update on Autoimmune Hepatitis」にも参加しました。AIHは欧米と日本ではHLAや治療法が全く違っており,慈恵医大の銭谷先生も含め,討論することで理解を深め,わが国から独自の研究・開発が必要と感じました。その他,NASHや肝線維化に対する演題も多く,肝硬変とサルコペニアや腸内細菌叢の話題もみられました。
ボストン
ボストンは,米国で最も古い歴史を誇る都市のひとつで,紅葉と海景色の美しさは随一です。地下鉄と徒歩で観光ができ,シーフードの宝庫でもあります。学会の後に新潟大学や順天堂大学静岡病院の先生と共にロブスターを囲みながら討論しました。
また,小澤征爾氏が長年在籍して,日本でも有名なボストン交響楽団を高橋先生と拝聴しました。異国の分化にも触れ,充実した日々を過ごしました。
 |
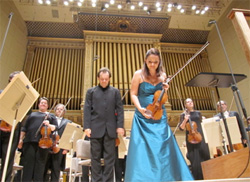 |
| 他大学の先生との食事会 | ボストン交響楽団 |
おわりに
私の国際学会への参加は2003年が最初で,米国消化器病週間(Digestive Disease Week:DDW)に入澤先生や澁川先生,若槻先生と参加させていただきました。SARS流行のためにN95を着用して空港入りしたことを懐かしく思います。
今回で8回目の参加となりましたが,肝臓医にとってAASLDに参加することは,最新知見を整理し理解を深めるとともに,自分の研究の世界への発信と再評価を行い,これからの研究の方向性を定めていくうえできわめて有意義であると思われます。
また口頭発表では,英語力不足のためいい研究をしても理解されないことが多々あるように思われ,日々英語力を磨く必要があると痛感しました。さらに,自分の発表を通じて米国の研究者と新たな出会いを産むことにも特に意義が大きいと思います。
今回このような機会を頂き,日頃からご指導を頂いております大平教授をはじめ,同門の先生方,研究にご協力頂き,学会中の業務を負担していただいた医局員の皆様に感謝申し上げます。